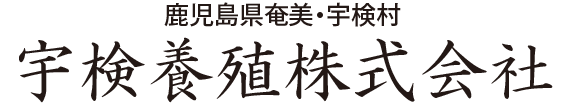遅ればせながら年賀状の話である。今年の年賀はがきのお年玉懸賞に、なんと2等賞が当たったのである。年賀状のお年玉懸賞には1等から3等まである。1等、2等は宝くじ並みの倍率でとても無理だろうと、毎年、はなから諦めている。一方、3等の切手シートはいつも10枚程度は獲得しているので、これを楽しみに今年も新聞でチェックした。今年はちょうど10枚当選しており賞品の引き換えに近くの郵便局に持ち込んだ。
なじみにしている局員が確認してくれる。そうしたところ 「2等も当たっていますよ!」と教えてくれた。2等はちゃんとチェックしなかったのだ。2等の当選番号は「2832」、3等は末尾の数字が「86」「65」「32」である。「32」と「2832」が重複当選していたのである。当たる確率は、1等が100万本に1本<1087本>、2等は1万本に1本<10万8795本>だそうである。万年3位から抜け出して2位に浮上した。この調子で来年は・・・と高望みするクセがある。いや、人間、感謝と謙虚さが大切だ、1万本に1本というのは大変なことだと思い直した。
ところで、年賀状が届くまでの成り立ちを考えてみた。
まず、年賀はがきを郵便局で購入する。年賀状離れや郵便料金の値上がりで、今年の正月の年賀状の配達枚数は大幅に減ったそうである。「年賀はがきだけは特別料金で安くしたら」という意見が新聞の投書欄に出ていた。同感である。
年賀状の図案を、長いつきあいのデザイナーに相談する。干支(えと)に因んだ写真を載せるのがえびおじさんのやり方で、昨年は龍の形になびく雲を載せた。しかしながら今年は「 へび 🐍 」である。えびおじさんはどうもへびが苦手だ。だいいち、写真がない。「困った困った、こまどり姉妹」である。これは昭和のおじさんたちのギャグだ。もう一つ、「しまった、しまった、島倉千代子」というのもある。 ああ、困ったえびおじさんである。
しかし、よくよく考えれば、干支の写真にこだわることはないのでは・・・ 思い至ったのが宇検村の野山に咲く月桃の花である。梅雨どきの花で、その楚々とした姿は何枚も撮ってある。これなら、もらった方も喜んでくれるのではないだろうか。デザイナーと何回かやり取りして、写真の大きさや手書き部分のスペースを決めて完成である。印刷だけだと味気ないので必ず手書きのひと言を添えることにしている。
できあがったデザインを年賀はがきとともに、知り合いの印刷屋に持ち込む。
「この忙しい時期に年賀状を書かねばならないとは何と矛盾していることか」とボヤキつつ大晦日の夕方に書き終える。ポストにどんと投げ込む。これでようやく正月がやって来るという大いなる解放感である。
年が明けると、ポストマンが配達にやって来る。
断捨離と称して年賀状をやめる人も多く届く賀状も微減傾向である。しかし、出すのをやめてしまうとその人との糸が切れて顔も忘れてしまいそうな気がする。ということも続けているひとつの理由だが、早い話、若者たちが「スマホでつながっていないと不安だ」という心理と似てなくもない。
正月からしばらくするとお年玉の抽選が行われ、再び、郵便局を訪ねるわけだが、年賀状にまつわるこの一連の流れは、それぞれに関わっている人たちの分業の集まりのようにも思える。循環と言えなくもない。うまい具合にお金も気持ちも回っているのである。
さて、お年玉の賞品である。1等は現金30万円、 2等はふるさと小包<米やカレーなど40種類の品からの選択である。5000円相当くらいか?>である。落差が大きすぎるではないかと、またまた、煩悩がムクムクと頭をもたげてきた。「いやいや、足るを知ることが大切だ。感謝の気持ちが足りない」と自らを戒める。貪(むさぼ)るなかれ、である。
免許証での本人確認の上、申し込んだのは「青森のりんごジュース」。手元に届くのはひと月ほど先になるらしい。この幸せをもたらしてくれたのは沖縄に住む友人からの年賀状である。ひょっとしたら、えびおじさんの年賀状も誰かに幸せを届けているかも知れない。<えびおじさん>

やぶつばき